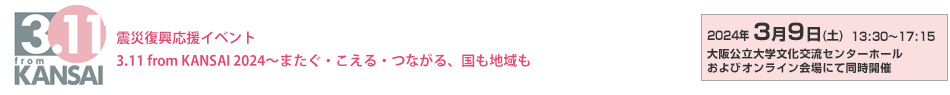| 2025/3/1 | ふりかえり、いまを検証する 3.11 from KANSAI 2025 開催決定! |
「3.11 from KANSAI」は東日本大震災の翌年から、3月11日の直近の週末に大阪で開催してきました。毎年東北からゲストをお招きして「東北のいま」を学ぶほか、熊本地震や西日本豪雨、能登半島地震などその後の災害にも心を寄せ、これからの「日頃の備え」や「関西から何ができるのか」を議論する機会としています。
東日本大震災から14年となる今回は、第1部で、岩手・宮城・福島で被災経験を持ちながら支援活動にも携わってこられたゲストをお招きし、改めて「東日本大震災とは何であったか」を回想することとしました。また、第2部で、東日本大震災を境に災害対応や支える側の社会がどのように変化してきたのかを、市民活動・災害法制・避難者支援のそれぞれの立場から検証します。
今年は阪神・淡路大震災から30年の節目の年でもあります。阪神・淡路大震災の頃と比べ、いまの日本は人口構成や経済構造がすっかり収縮しており、能登半島地震への対応をみても明らかなように、ひとたび大規模な災害に見舞われると基本的なニーズへの対応すら難しい状況となっています。阪神・淡路大震災では地域での助け合いやボランティアによる支援が注目されましたが、社会が大きく変化する中、互助や共助だけで被災者を支えることは困難な状況となっています。東日本大震災から14年の節目にあたり、東北復興のため、またこれからの災害に備えるために関西からできることを、みんなで考えましょう。
| 日時 | 2025年3月8日(土)13:30-17:30 |
|---|---|
| 会場 | 大阪公立大学文化交流センターホールおよびオンライン会場にて同時開催 大阪市北区梅田1-2-2-600(大阪駅前第2ビル6階) 最寄り駅:JR東西線「北新地駅」下車徒歩約3分、地下鉄四つ橋線「西梅田駅」下車徒歩約5分など |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 大阪公立大学文化交流センターホール 100人 オンライン会場 制限なし |
| 対象 | 「3.11」や東北へ思いを寄せる人、関西での備えを考えている人、関心のある方ならどなたでも |
| 主催 | ([構成団体]一般財団法人ダイバーシティ研究所/認定NPO法人トゥギャザー/NPO法人遠野まごころネット/社会福祉法人大阪ボランティア協会[事務局]) [運営協力団体:おおさか災害支援ネットワーク(OSN)] |
| 協賛企業(五十音順) | 近畿労働金庫、産経新聞社、サントリーホールディングス株式会社、宗教法人真如苑、東武トップツアーズ株式会社大阪法人事業部 |
| コンセプト | 「忘れない」:復興活動はこれからも続く。東日本大震災の「いま」を知り、風化させない。 |
| 3.11 from KANSAI 2025の強化テーマ | 「ふりかえり、いまを検証する」 |
| 登壇者・プログラム | 第1部「The・回想 3.11」 東北3県からゲストをお招きし、3.11の発生直後からの様子を回想しながら「できたこと」「できなかったこと」をふりかえり、いまの地域の課題を見つめ直します。 ・阿部 忠義(あべ ただよし)さん|一般社団法人 南三陸研修センター 代表理事 ・鹿野 順一(かのじゅんいち)さん|特定非営利活動法人 アットマークリアス NPOサポートセンター代表理事 ・高橋 美加子(たかはし みかこ)さん|株式会社北洋舎クリーニング 取締役会長、まなびあい南相馬代表、福島県中小企業家同友会相双支部相談役(2011-2014年度会長)、南相馬こどものつばさ理事 <進行>長井 健悟(ながい けんご)さん|関西学院大学社会学部4年生、関西学院大学総部放送局
第2部「The・検証 2025」 3.11以降の社会変化をふまえ、これからの被災者支援のあり方について、専門家・当事者・支援者の目線からともに考え、これからの地域の課題や可能性を検証します。 ・津久井 進(つくい すすむ)さん|兵庫県弁護士会、弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所 ・古部 真由美(ふるべ まゆみ)さん|まるっと西日本 代表世話人 ・谷内 博史(やちひろふみ)さん|明石市政策局SDGs共創室市民とつながる課 係長・ファシリテーション担当、特定非営利活動法人NPO政策研究所 理事、七尾未来基金設立準備会 理事(現・一般財団法人能登里山里海未来財団)、金沢交響楽団、オルビス能登オーケストラ ファゴット奏者 <進行>吉岡 恵麻(よしおか えま)さん|関西学院大学 社会学部、関西学院大学総部放送局
プログラム 13:00- 開場・受付開始 13:30-(15分) 開会挨拶 実行委員長 田村太郎/3.11 from KANSAI実行委員長 13:45-(5分) 祈り〜黙とう 13:50-(100分) 第1部「The・回想 3.11」 15:30-(10分) 休憩 15:40-(100分) 第2部「The・検証 2025」 17:20-(5分) 閉会挨拶 実行委員 17:25- 閉会 17:45頃- 懇親会(登壇者と参加者有志で開催。会場近くの飲食店にて、会費は4,000〜4,500円程度を予定) |
| 連携企画情報 |
「福島から避難されている方の第5回『交流カフェ』」 https://sasukene.jp/gathering/ 日時:2025年3月8日(土)13:30-16:00 会場:大阪公立大学文化交流センター・大セミナー室 運営:福島県県外避難者相談センター「サスケネ」
「買って応援!障害者福祉事業所商品2025」 被災地を含む障害者福祉事業所で作られた商品を買って応援!食べて満足!ぜひご利用ください。 <NPO法人トゥギャザーオンラインショップ> https://together1999.official.ec/ (受取可能商品:クッキー、米菓子、みかんゼリー、牛タンカレーなど) お申込み後、自動返信メールとは別メールにて送料を差し引いたお支払い金額をお伝えいたします。「買って応援!障害者福祉事業所商品2025」 |
| 参加申込方法 |
事前に参加申込みフォームよりお願いします。 |
「ふりかえり、いまを検証する 3.11 from KANSAI 2025」登壇者
第1部「The・回想 3.11」登壇者
◆阿部 忠義(あべ ただよし)さん|一般社団法人 南三陸研修センター 代表理事

<プロフィール>
元南三陸町職員37年勤務、復興キャラクター「オクトパス君」の発案者。
震災時は、町役場に勤務し産業振興行政に従事。震災直後、内陸部の公民館に異動し避難所支援業務の傍ら、全国各地から駆けつけるボランティアを積極的に受け入れ、その繋がりと応援の風を受けながら復興に向けた様々な地域活動に取り組み現在に至る。
<当時の活動や現在の取組み紹介>
震災直後、復興キャラクター「オクトパス君」などを制作するYES工房を起ち上げる。続けて、企業や学生が集う地域づくりの拠点となる一般社団法人南三陸研修センターを設立。
以来、宿泊研修施設いりやど及びYES工房の運営、農泊推進等に取り組み、地域の活力を産むための活動に奮闘中。あるいは社会実験の日々を過ごしている。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
震災で生き残った者として、必死になってこの町を良くするために、様々な事業活動に取り組んできた。上手くいっていないこともあるが、常に新しい光と風を取り入れ、これからも地域の仲間とともに強気で推し進めていきたい。いつどこで何が起きるかわからない昨今、環境の変化に対応できる心の備えだけは万全にしておきましょう。
2011.7.16麻布十番でのイベントに参加
盛り上がる小学校スタディツアー |
2011.7YES工房発足時の仲間
学生たちが弾ける地域実習 |
◆鹿野 順一(かの じゅんいち)さん|特定非営利活動法人 アットマークリアス NPOサポートセンター代表理事

<プロフィール>
1965年、岩手県釜石市生まれ。まちづくりや商店街活性化に携わり、2004年にNPO法人アットマークリアスを設立。2011年の東日本大震災後、支援活動を展開し、岩手連携復興センターの運営にも関わる。仮設住宅での見守り事業や地域DX推進に取り組み、現在はデジタル技術を活用した孤独・孤立予防や地域づくりを推進し、持続可能な地域社会の構築を目指している。
<当時の活動や現在の取組み紹介>
震災直後、安否確認や情報発信を行い、外部支援との橋渡しに取り組む。岩手連携復興センターの設立運営にも関わり、県内NPOのネットワーク構築や、広域での支援活動の調整を行った。その後、釜石市において仮設住宅や公営住宅での見守り支援を継続し、被災者の孤立防止に取り組む。現在は地域DXの推進を通じ、デジタル技術を活用した見守り支援や暮らしの質向上に取り組み、地域の未来を考えるプラットフォームづくりに挑戦している。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
震災直後の混乱の中で「できたこと」と「できなかったこと」を今改めて見つめ直すことで、次世代の防災や地域づくりに活かせる教訓があると考えます。地域の支え合いやデジタル活用が新たな課題解決の鍵となる今、過去の経験を振り返りながら、これからの地域のあり方を共に考える機会にしたいです。
仮設住宅団地での見守り活動の様子 |
◆高橋 美加子(たかはし みかこ)さん|株式会社北洋舎クリーニング 取締役会長、まなびあい南相馬代表、福島県中小企業家同友会相双支部相談役(2011-2014年度会長)、南相馬こどものつばさ理事

<プロフィール>
2011年3月11日の東日本大震災による原発事故で30キロ圏内になり、会社閉鎖、全従業員避難という事態に陥り(当時、代表取締役)、私自身も、原発建屋の相次ぐ爆発で3月15日から1週間は避難しました。しかし、会社とコミュニティ再生のために3月22日に南相馬市に戻り、地域を消滅させないためにと4月に若者2人と「つながろう南相馬」を立ち上げ、市民活動をはじめました(3年間かかわる)。その後、2016年1月に心のケアを中心に据えた「まなびあい南相馬」を立ち上げ代表として現在も活動しています。
<当時の活動や現在の取組み紹介>
・「つながろう南相馬」:震災直後、人口が7万人から1万人を切るまでに減少し市民の心が荒んでいきそうになったので気持ちの立て直しが必要と、企業に協力をしてもらって「ありがとうから始めよう」と「ふるさと再生!!こどもたちに未来!!」をスローガンにした旗を町中に立て、市役所、消防、警察、自衛隊に感謝の気持ちを書いたポスターを届ける活動からスタートし外部発信もし、支援者と市民をつなぐ活動をしました。
・「まなびあい南相馬」:震災から5年が過ぎ暮らしの負の変化が多岐にわたって表出してきた時期で、丁度始まった復興庁の心の復興事業に応募する形でメンタルケアを中心にした活動をしようと設立しました。
活動内容は、聞き書き、ファシリテーション、演劇、セルフケア、セラピーなどのワークショップ。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
震災から14年になり、今になってPTSDのような心理状態が表れてきている人もいます。また、当時子どもだった人が親世代になり、子育ての姿に変化がみられるとの声も聞かれます。助成金に該当しないこのような現象の解決のため、市民自ら学びあい、心の足腰を強くし、解決力を身に着けて違いを認め合う柔らかな社会を作っていきたいと思っています。
親子身体詩ワークショップで交流 |
◆進行:長井 健悟(ながい けんご)さん|関西学院大学社会学部4年生、関西学院大学総部放送局

<プロフィール>
大阪府豊能町出身。高校までスポーツ6競技をしてきたが大学から放送部に入部。放送部での活動、大学での授業、就職活動を通じて災害・防災に関心を持ち、防災士の資格を取得。東日本大震災当時は小学2年生。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
能登半島地震の際、何もできない自分に無力感を感じた。浪江を訪ねた際、潮風になびくススキを見て自分の無知を知った。いつ起こるかわからない災害に備えるためにも災害を人に伝えるためにも、正しい知識を得ることは大切です。大学生らしく学ぶ姿勢で臨みます。
浪江・請戸小学校を訪問 |
第2部「The・検証 2025」登壇者
◆津久井 進(つくい すすむ)さん|兵庫県弁護士会、弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所

<プロフィール>
阪神・淡路大震災の直後に弁護士登録をして、以来、約30年にわたり被災者支援に携わる。特に被災者支援に関する制度等の支援や、311をはじめとする全国各地の被災地への後方支援を続けてきた。原発事故の避難者に対する支援も続けている。著書に『大災害と法』『災害ケースマネジメント◎ガイドブック』など
<当時の活動や現在の取組み紹介>
日本弁護士連合会の災害復興支援委員会の前委員長として法律支援に関わる。原発賠償ひょうご訴訟の弁護団長として、兵庫への避難者を支援する。また、「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」の共同代表として、能登半島地震の支援に入っている。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
現在の災害の世界では、一人ひとりが大事にされていない。被災とは災害によって人権を失ったり危うくされることで、復興とは被災者の人権を回復することである。311の被災地をはじめ、被災地でたった一人が取り残されることのないように対応していきたい。そのためには、ボランティアの本質である「自発性」の回復を訴えていきたい。
弁護士登録直前のボランティア活動 |
◆古部 真由美(ふるべ まゆみ)さん|まるっと西日本 代表世話人

<プロフィール>
大阪生まれ。2011年に東日本大震災の広域避難者支援団体(まるっと西日本)設立に関わり、代表世話人。東日本大震災以降、関西で東日本大震災の広域避難者の生活再建支援に従事。現在は、能登半島地震の広域避難者への訪問や相談ボランティアにかかわる。「第43回 産経市民の社会福祉賞」受賞
<当時の活動や現在の取組み紹介>
東日本大震災の広域避難者相談は減ったものの、精神障害や発達障害、一人親世帯の再建は長期化しています。能登半島地震の広域避難者からの相談や訪問の依頼も、高齢者や女性が多く、脆弱性の高い人にサポートが必要です。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
大阪は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、ウクライナの被災者を受け入れ、現在も多くの人が大阪で暮らしています。将来予想されている南海トラフ地震の発生時には、大阪に住む私たちは、避難者も受け入れながらも、自分たち自身も被災し、避難する可能性があるのです。避難について知る事は、将来の自分自身の防災につながります!
東日本大震災の広域避難者への同行支援
東日本大震災の広域避難者交流「3月の黙とう」 |
仮設住宅への情報誌の配布、カレンダーの手渡し
関西で開催した能登半島地震避難者のための「ふるさと集会」 |
◆谷内 博史(やち ひろふみ)さん|明石市政策局SDGs共創室市民とつながる課 係長・ファシリテーション担当、特定非営利活動法人NPO政策研究所 理事、七尾未来基金設立準備会 理事(現・一般財団法人能登里山里海未来財団)、金沢交響楽団、オルビス能登オーケストラ ファゴット奏者

<プロフィール>
1971年生まれ。コミュニティ財団、NPOシンクタンク、まちづくり会社を経て、石川県七尾市のまちづくりコーディネーター、富山県氷見市任期付職員としてファシリテーション・市民協働を担当。その後、石川県金沢市任期付職員として市民活動サポートセンター所長を6年間勤めた。2024年4月より、明石市のファシリテーター専門職員として着任。
<当時の活動や現在の取組み紹介>
2007年能登半島地震では地震被害のあった酒蔵の日本酒など「BUY NOTOキャンペーン」で地元産品を買って応援!という活動に奔走。3.11当時は「浪江のこころ通信」で金沢市内避難者への取材ボランティアとして活動した。能登半島地震では能登島にて被災し、避難所運営、外部団体との被災地をつなぐ活動、ボランティア活動情報共有のファシリテーターなどをつとめた。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
30年前は大学ボランティアセンター立ち上げ、被災地と学生ボラのコーディネートをしたが、今は被災当事者にもなって再び関西の地で暮らすことに。
今は、神戸でのチャリティコンサートの寄付を能登の復興財団へ、被災して休止していた能登の子どもオーケストラ活動への支援に汗をかいている。災害は人と人がつながれる、まちづくりの永遠機関なのかも。
神戸でのチャリティコンサート |
神戸でのチャリティコンサート |
◆進行:吉岡 恵麻(よしおか えま)さん|関西学院大学 社会学部、関西学院大学総部放送局

<プロフィール>
兵庫県出身で、幼少期から授業などで阪神・淡路大震災や防災について学んできました。大学2年生のときは福島県浪江町に1週間滞在し、福島第一原発内部の見学や被災された方々のお話を伺う機会がありました。この経験を通じて防災への関心が一層深まり、防災士の資格を取得。今年4月からはアナウンサーとして、防災・減災に貢献できるよう学びを続けています。
<ご自身の想いや伝えたいこと>
今回のイベントを通じて被災地の歩みや未来について、そして自分に出来ることは何かを皆さんと一緒に学びたいと思っています。アナウンサーとしても震災の記憶や教訓を受け継ぎ、どのように後世に伝えていくべきなのかを考え続けられる人でありたいと思います。精一杯務めさせていただきます!どうぞよろしくお願いいたします。